ボリンジャーバンドは、FXのテクニカル分析でよく使われる指標の一つです。価格の変動幅(ボラティリティ)を視覚的に捉えることができ、相場の過熱感やトレンドの勢いを判断するのに役立ちます。本記事では、ボリンジャーバンドの基本的な仕組みや活用方法、注意点まで詳しく解説します。

ボリンジャーバンドとは?
ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心に価格の変動範囲を示すバンド(帯)を表示する指標で、1980年代にジョン・ボリンジャー氏が考案したものであり、価格の変動幅(ボラティリティ)を測るのに最適です。そして、バンドの広がりや縮まりから相場の勢いやトレンドを判断できます。
ボリンジャーバンドは、下記の3本の線(バンド)で構成されます。
- ミドルバンド(中央線):移動平均線(通常は20日)
- アッパーバンド(上の線):移動平均線+標準偏差(σ)
- ロワーバンド(下の線):移動平均線-標準偏差(σ)
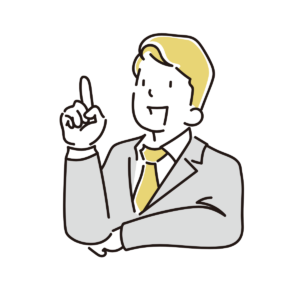
ボリンジャーバンドの基本的な考え方
ボリンジャーバンドは、価格の90%以上がバンド内に収まるという統計的な特徴を持っています。これを利用して、相場の過熱感や反転のタイミングを判断します。
バンドの特徴と意味
- バンドが広がる(エクスパンション):相場のボラティリティが高まり、大きな値動きが起こるサイン
- バンドが縮まる(スクイーズ):相場のボラティリティが低下し、次の大きな値動きの前兆
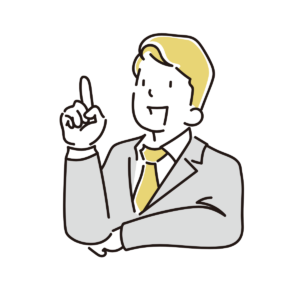
ボリンジャーバンドの活用方法
ボリンジャーバンドは、主に以下の2つの方法で活用されます。
1.バンドウォーク(トレンドの継続)を利用する
価格がアッパーバンドやロワーバンドに沿って動く状態を「バンドウォーク」と呼びます。これは、強いトレンドが発生しているサインです。
エントリーポイントの例
- 上昇トレンドの場合:価格がアッパーバンドに沿って上昇 → 買いのチャンス
- 下降トレンドの場合:価格がロワーバンドに沿って下降 → 売りのチャンス
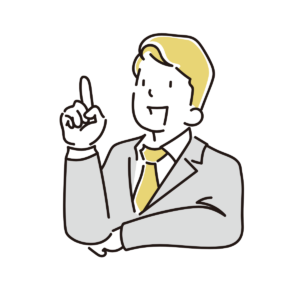
2.バンドの反発(逆張り)のサインとして使う
ボリンジャーバンドは、価格がバンドの端に接触すると反転する傾向があることから、逆張りのトレードにも活用されます。
エントリーポイントの例
- 価格がアッパーバンドに接触 → 売りエントリー(下降を狙う)
- 価格がロワーバンドに接触 → 買いエントリー(上昇を狙う)
ただし、強いトレンドが発生している場合、バンドに接触しても価格がそのまま進むことがあるので注意が必要です。
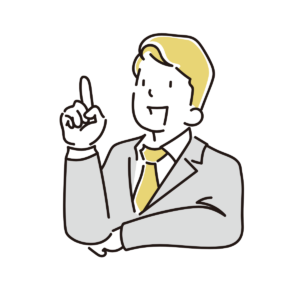
ボリンジャーバンドのメリット・デメリット
メリット
- 相場のボラティリティ(変動幅)を簡単に把握できる
- トレンドの勢いや転換点を視覚的に判断できる
- トレンドフォロー(順張り)にも逆張りにも活用できる
デメリット
- トレンド相場では逆張りの判断が難しくなる
- バンドの広がりや縮まりのタイミングを完全に予測するのは難しい
- 他のテクニカル指標と組み合わせないとダマし(フェイクシグナル)に引っかかることがある
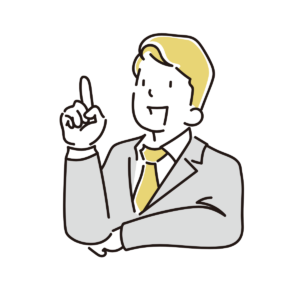
ボリンジャーバンドを活用するポイント
- トレンドの方向を見極めるために移動平均線と組み合わせる
- RSIやMACDなどのオシレーター系指標と併用してダマしを回避
- バンドの広がり(エクスパンション)と縮まり(スクイーズ)を意識する
ボリンジャーバンドを使いこなすことで、相場の勢いや反転のサインをより正確に判断できるようになります。ぜひ、実際のチャートで活用してみましょう。
